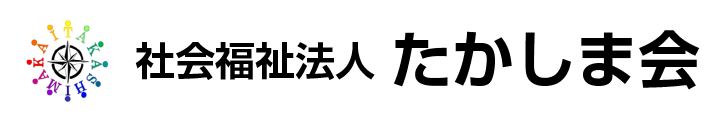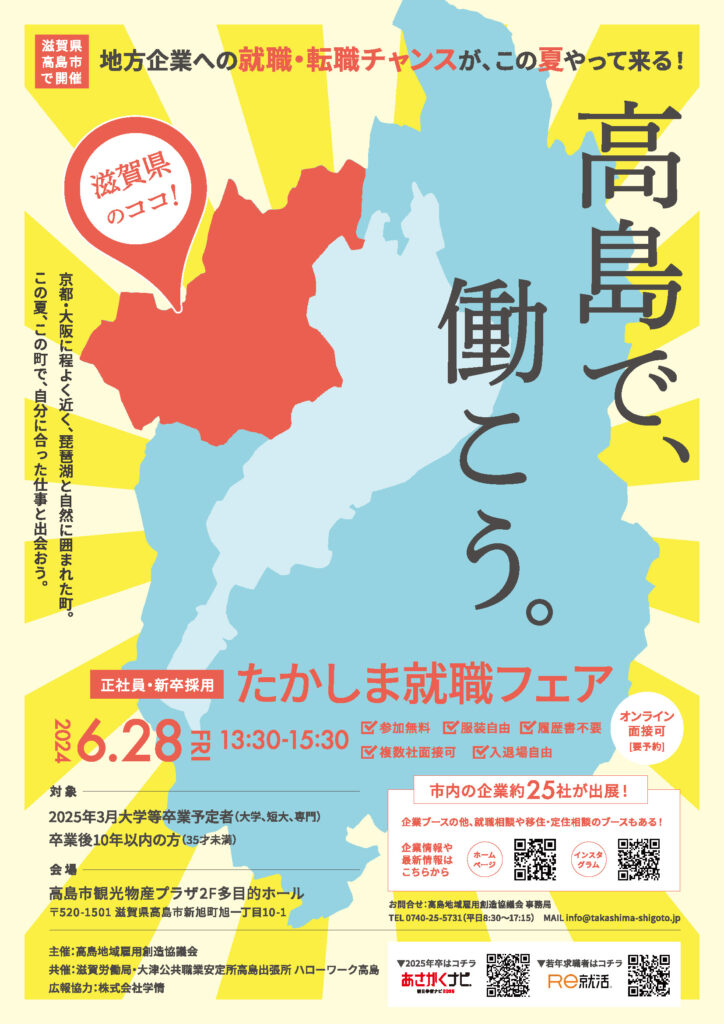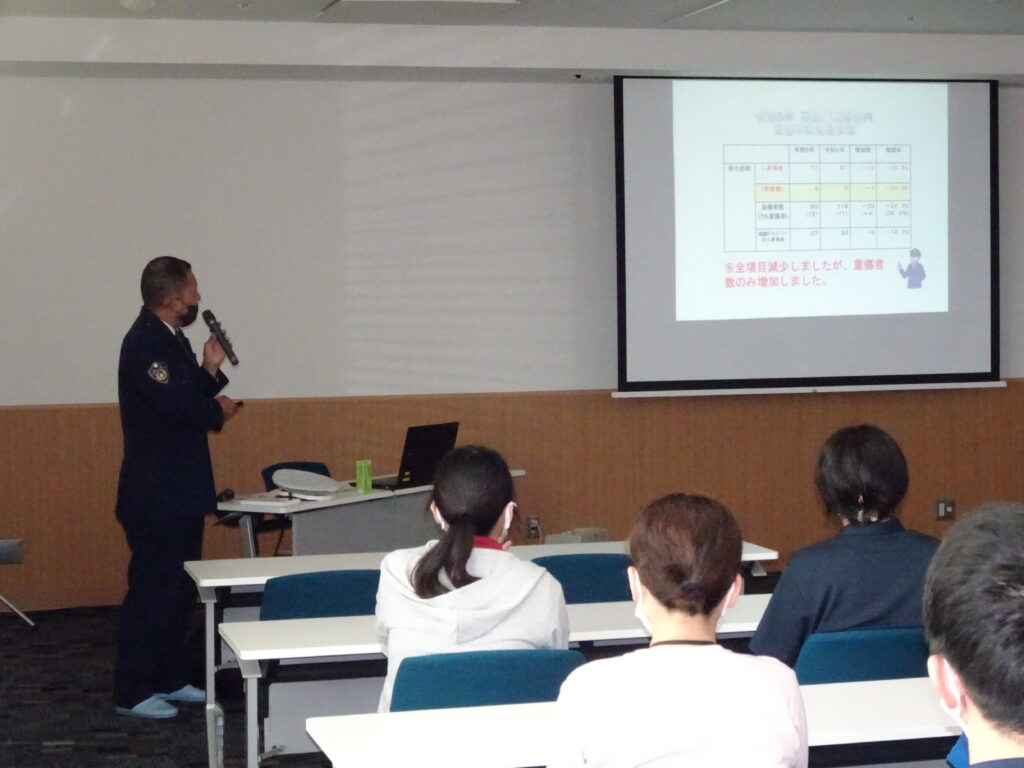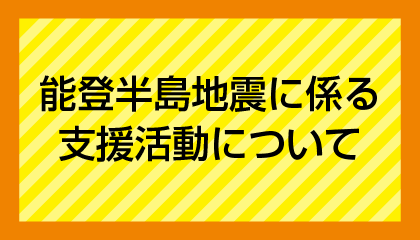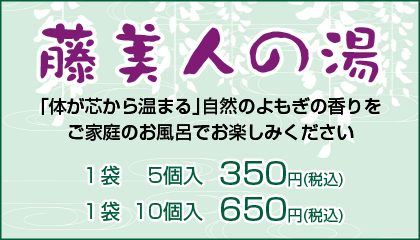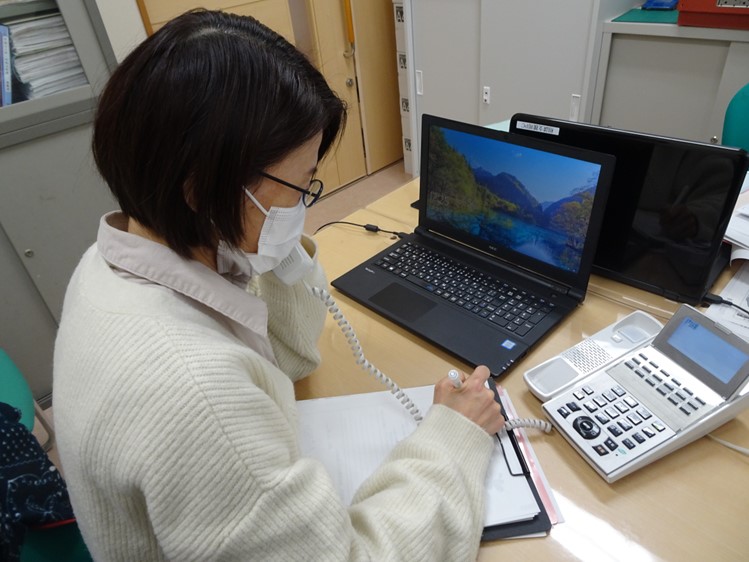誰もが自分らしく
生きられる社会をめざす
障がい者支援や介護のことなら
社会福祉法人たかしま会
へお気軽にご相談ください。
社会福祉法人たかしま会は、養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、障がい者支援施設、障がい者デイサービスセンター、就労継続支援B型事業所、グループホーム、相談事業所を運営しています。
私たちは地域団体や地域住民と一緒に行事を開催したり、さまざまな地域貢献事業にも力を入れています。
たかしま会は地域とともに新しい価値を創造し続けることで、その挑戦の先に利用者や地域で暮らす方々の豊かな生活を実現したい、それが私たちの願いです。
最新情報
社会福祉法人たかしま会 理念
- 近江聖人中江藤樹の遺徳を仰ぎ「誰でも努力すれば立派な人間になれる」という創設の精神を尊び、事業運営を行っていきます。
- 福祉サービスの利用者に対して、尊厳を保持しかつ幸福や安全を保障するとともに、各々の能力に応じた自立支援を行い、利用者本位の良質かつ適切なサービスを提供していきます。
- 地域福祉推進のため地域の拠点事業所としての質的向上に努め、地域住民との相互理解や協力を得て、地域の要望に応じた事業を展開し、地域の福祉向上に寄与していきます。